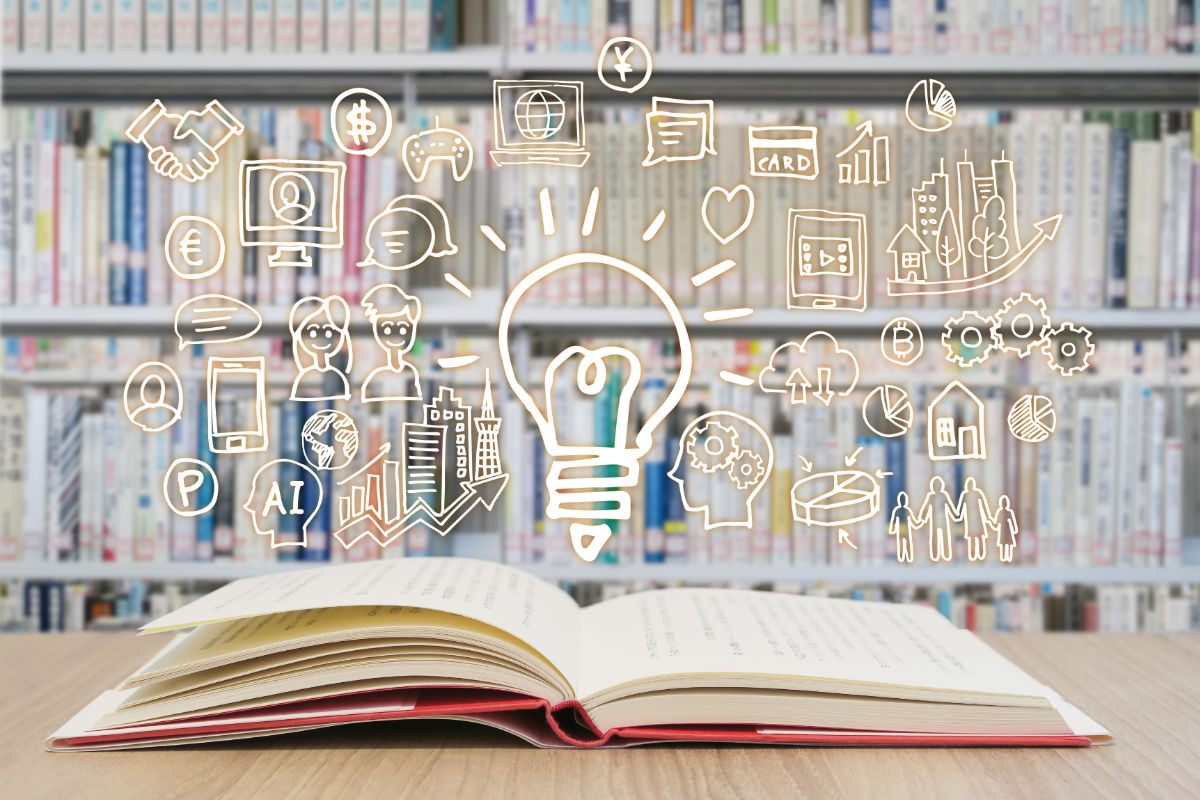はじめに:その「起業したい」、本当に大丈夫?
なぜ起業家になりたいのか?
「起業したいけど、良いアイデアが思い浮かばないんだよね…」
もしあなたが今、こんな風に悩んでいるなら、少しだけ立ち止まってこの記事を読んでみてください。
一見すると、多くの人が抱える悩みに聞こえるかもしれませんが、実はこの言葉の裏には、起業という道のりの「甘くない現実」と、あなたがまだ気づいていないかもしれない「大きなリスク」が隠されています。
メディアで見る起業家は、自由な働き方を手に入れ、情熱を仕事にし、自分の船の船長として輝いて見えますよね。その姿に憧れるのは、とても自然なことです。
でも、そのキラキラしたイメージの裏側には、ほとんど語られることのない厳しい現実があります。統計データが示す圧倒的な失敗の確率、そして想像を絶するような心とお金の負担です。
この記事で一番伝えたいことは、「起業家になること」自体をゴールにしてしまうことの危うさです。
本当の起業家とは、かっこいい職業やステータスを選ぶことではありません。『この問題』をどうしても解決したい!『このビジネス』で成功したい!という、内側から湧き上がる強い衝動の結果、自然とたどり着く道なのです。
だからこそ、「アイデアがない」という状態は、単に「ひらめきがない」ということではありません。それは、起業に絶対不可欠な「こだわり」が欠けているという、危険なサインなのです。こだわりがなければ、起業という嵐の海を乗り越えるのは不可能に近いからです。
「プッシュ型」ではなく「プル型」?
まず、なぜ「アイデアはないけど起業したい」と思ってしまうのか、その気持ちの背景を探っていきます。多くの人は、今の仕事への不満、つまり「ここから抜け出したい」という「プッシュ型」の気持ちに背中を押されています。
上司や組織のルールから自由になりたいという気持ちは、痛いほどよく分かります。しかし、この「逃げたい」という気持ちだけでは、起業の土台としてはあまりにも脆いのです。
なぜなら、それは「逃げること」が目的になっていて、どこに向かいたいのかという「目的地」がないからです。
一方で、成功した起業家たちは、特定の社会問題やお客さんの不満といった「プル型(引き寄せられる型)」の動機に強く引かれています。
例えば、ユーグレナ社はバングラデシュの栄養問題を解決したいという思いに突き動かされ 、タイミー社は創業者自身の不便なアルバイト体験から生まれました。
彼らの原動力は、「この問題を解決せずにはいられない」という強烈な使命感です。この「プル型」の動機こそが、次から次へと襲いかかってくる困難に立ち向かうための、折れない心の支えになるのです。
この記事は、単に「やめておけ」と脅かすものではありません。甘い夢から一度目を覚まし、本当に価値のある挑戦へと踏み出すための、データに基づいたリアルな地図です。
さあ、一緒に起業の現実をのぞいてみましょう。
単に「起業のアイデア」の見つけ方を知りたい方は下記の記事(スモールビジネス編とスタートアップ編に分かれています)をご覧ください。
なぜ「アイデアがないのに起業したい」と思ってしまうのか?
起業したいと願いながら、具体的なビジネスアイデアが浮かばない。その気持ちの裏には、単に「ひらめきがない」というだけでなく、もっと根深い理由が隠されています。
それは、現代社会が作り上げた「起業」のイメージと、あなた自身の心の中にある不安や知識不足が、複雑に絡み合った結果なのです。
「今の場所から逃げたい」気持ちと「起業家」という響きへの憧れ
「アイデアはないけど起業したい」と考える人の多くは、今の状況からの「逃げたい」という気持ちを一番の動機にしています。彼らが本当に求めているのは、特定のビジネスで価値を生み出すことよりも、「起業家」という自由でカッコいい存在になることそのものかもしれません。これは、「起業すること自体が目的になっている」状態で、実はとても危険なサインです。
最近の「働き方改革」や、リモートワーク、副業の解禁といった流れの中で、「自分らしい働き方がしたい」という気持ちはどんどん強まっています。会社の堅苦しいルール、人間関係のストレス、正当に評価されない不満など、会社員として働く中で感じる窮屈さから抜け出したいと願うのは、当然のことでしょう。
しかし、この「プッシュ型」の動機は、起業のエネルギー源としては少し弱いのです。なぜなら、その力は「何かを成し遂げたい」というポジティブな情熱ではなく、「何かから逃れたい」というネガティブな反発力だからです。
さらに、テレビやSNSは起業家の「ステータス」をキラキラしたものに見せがちです。成功した創業者のストーリーは、自由と富、そして社会的な名声のシンボルとして語られ、多くの人がその「役割」自体に憧れを抱きます。
しかし、そこで憧れているのは、多くの場合「創業者」という肩書きがもたらす華やかなイメージであって、その裏にある地味で過酷なビジネス作りのプロセスではありません。
この罠にはまってしまうと、ビジネスで一番大切な「お客さんに価値を届けること」よりも、自分が「起業家」と呼ばれることに満足してしまいます。
それは、目的地(価値の創造)を決めずに、乗り物(会社という箱)だけを欲しがるような、本末転倒な状態なのです。
アイデアが生まれない3つの壁:「自分には無理」という思い込み、知識不足、そして思考の停止
では、なぜ具体的なアイデアを生み出すことができないのでしょうか。そこには、心と経験の両面からくる、いくつかの壁が存在します。
壁① 自分自身でブレーキをかけてしまう心と、失敗への恐れ
多くの人は、「失敗したらどうしよう」「自分なんかにできるわけがない」という気持ちから、無意識のうちに考える範囲を自分で狭めてしまっています。新しいことへの挑戦には不安がつきものですが、その不安が、アイデアのタネが芽を出す前の土をカチカチに固めてしまうのです。
壁② ビジネスの“現場”に関する経験や知識の不足
ビジネスアイデアは、ある日突然、魔法のように降ってくるものではありません。それは、特定の業界や分野を深く知っているからこそ生まれるものです。「お肉を加工する業者さん」の存在を知らなければ、その業者さん向けの便利なサービスを思いつくことはできませんよね。つまり、アイデアとは「誰かの困りごと」を見つける力であり、それを見つけるためには、その世界のことをよく知っている必要があるのです。
壁③ アイデアが詰まってしまう『創造性のブロック』
強いストレスや疲れ、あるいは「こうあるべきだ」という固定観念は、自由な発想の邪魔をします。特に、「起業しなきゃ!」というプレッシャーの中で無理やりアイデアを絞り出そうとすると、頭はどんどん固くなり、新しい見方ができなくなってしまいます。
これらの壁が組み合わさることで、「アイデアがないけど起業したい」人は、起業へのステップを根本的に間違えてしまいます。
ビジネスの仕組みとは
本来、起業は【問題を発見する → それを解決するアイデアを思いつく → ビジネスとして始める決断をする】という順番で進むべきです。
しかし彼らは、【ビジネスとして始める決断をする → アイデアを探し始める】という、全く逆の道をたどろうとします。
これは、ビジネスが何のためにあるのかを理解していない証拠です。
ビジネスとは、お客さんの問題を解決して、その対価としてお金をいただく仕組みです。その「何のために」という目的(問題解決)が決まる前に、「どうやって」(会社を作る)を決めるのは、何を作るか決まっていないのに工場を建てるようなもの。
この間違ったプロセスでは、結局、流行りに乗っただけの真似事や、自分のスキルや情熱とは全く関係のない、うわべだけの弱いアイデアしか生まれてこないのです。
数字で見る、起業の甘くない現実
起業という選択は、華やかな成功物語の裏で、驚くほど多くの挑戦者を飲み込んできました。
その現実は、単なる「気合い」や「根性」で語れるものではなく、冷たい数字と、失敗の具体的な理由、そして挑戦者自身にのしかかる「見えないコスト」によって成り立っています。
この章では、甘い夢を一旦脇に置いて、起業という道のりがどれだけ厳しいものなのかを、データをもとに見ていきましょう。
生存率データが示す「2つの世界」
起業後の会社がどれくらい生き残るかを示すデータは、一見すると矛盾しているように見えます。この矛盾を正しく理解することが、現実を知る第一歩です。
中小企業の生存率
まず、比較的「希望が持てる」データとして、日本の中小企業の生存率があります。
中小企業庁の調査によると、起業して1年後には95.3%が、3年後でも88.1%、そして5年後ですら81.7%もの会社が事業を続けています。これは、欧米の国々と比べても高い数字で、日本のビジネス環境が安定しているように見えます。
しかし、この数字には大きな「からくり」があります。この統計には、個人で堅実に稼ぐ人や急成長を目指さない小さな事業(スモールビジネス)がたくさん含まれているのです。
そもそもスモールビジネスで起業を考えていたんだけど…、一人起業を考えていたんだけど…という方はこちらをご覧ください。
スタートアップの生存率
多くの人がメディアで見て憧れるような、革新的なサービスで世界を変える「ベンチャー型」のスタートアップの現実は、これとは全く違います。
ベンチャーキャピタルなどから大きな資金を集めて急成長を目指すスタートアップの世界では、現実は遥かに過酷です。
ある調査データは衝撃的で、ベンチャー企業の5年後の生存率はわずか15.0%、10年後にはなんと6.3%にまで落ち込みます。これは世界的な傾向とも一致しており、 スタートアップの約90%が最終的に失敗すると言われています。
特に、設立から 2年目から5年目の間に、全体の70%もの企業が失敗に追い込まれます。この期間は、最初の資金が尽き、ビジネスモデルの真価が問われる「死の谷」と呼ばれています。
あなたが夢見る起業は、どちらの世界ですか?
メディアが描く華やかな成功物語に憧れる「アイデアなき起業志望者」は、知らず知らずのうちに、後者の、成功率が1割にも満たない厳しいゲームに足を踏み入れようとしているのです。彼らが期待している「8割が成功する世界」は、そこにはないのです。
なぜ9割も失敗するのか?根本的な原因はたった一つ
では、なぜこれほど多くのスタートアップが失敗してしまうのでしょうか。その原因は色々ありますが、実はそのほとんどが、たった一つの根本的な問題から派生した「症状」に過ぎません。
スタートアップが失敗する最大の原因。それは世界中の調査が口を揃えて指摘する「市場のニーズがなかった」、つまり「お客さんが本当に欲しがるものを作れなかった」ことです。
統計によれば、失敗した会社の34%から42%が、この問題が原因だとされています。これは、「アイデアがないまま起業する」ことが、なぜ致命的であるかを何よりも雄弁に物語っています。
解決すべき明確な問題意識なしにビジネスを始めれば、誰も欲しがらないものを作ってしまうのは、ごく自然な結果と言えるでしょう。
その他の主な失敗原因も、この根本的な問題から生まれる症状として理解できます。
- 資金が尽きる
失敗原因の第2位ですが 、これも多くの場合、市場が求めていない製品やサービスにお金を使いすぎた結果です。売上がないまま人件費や家賃だけが出ていき、やがて資金が底をつきます。 - チームの問題
仲間との対立や、良い人材が採用できないことも大きな原因です。事業がうまくいかず、将来が見えない状況がチーム内に不満や不安を生み、崩壊につながります。 - マーケティングの失敗・競争に負ける
解決すべき課題が曖昧で、お客さんに提供する価値がはっきりしていなければ、効果的な宣伝はできません。その間に、もっとお客さんのことを理解しているライバルに市場を奪われてしまいます。 - 計画性のなさや法律違反
ビジネスの根幹がグラついていると、経営者の意識は目先の資金繰りにばかり向いてしまい、法律を守ることや長期的な計画を立てるといった、当たり前で重要なことがおろそかになりがちです。
これは小さな会社だけの話ではありません。Amazonが作ったスマートフォン『Fire Phone』や、セブン&アイが始めた決済アプリ『7pay』のような大企業の失敗も、本質は同じです。お客さんが本当に求めている価値や、サービスに絶対に必要な条件(例えばセキュリティ)を深く理解しないまま世に出してしまった結果、莫大な投資が水の泡となりました。
会社の規模に関わらず、「お客さんが欲しがっていない」ことは、ビジネスにとって致命傷になるのです。
お金だけじゃない!起業家を襲う「業務地獄」と「心の危機」
困難の連続
起業の厳しさは、ビジネスそのものの難しさだけではありません。成功物語では決して語られない、創業者自身にのしかかる個人的な負担は、時に事業の成功を左右するほど大きいものです。
まず、日々の業務が想像を絶するほど大変だということ。会社員時代には考えられなかったような困難が次々と襲いかかります。
創業したばかりの会社は「信用がゼロ」なので、銀行からお金を借りるどころか、会社の銀行口座を作ることすら断られることがあります。
税金や社会保険といった事務手続きは驚くほど複雑で、創業者自身が膨大な時間を奪われる「つらい」作業です。
さらに、知名度も給料も大企業に劣るスタートアップが、優秀な人を採用するのは、本当に難しいことです。
そして、これら全ての困難の上に、精神的なプレッシャーが重くのしかかります。
起業は孤独な旅です。創業者は、事業がうまくいくかどうかわからないという終わりのない不安と、従業員やその家族の生活を背負うという重圧に押しつぶされそうになります。
少しでも事業が注目されれば、根も葉もない誹謗中傷に心を痛めることもあります。社内には、同じ立場で悩みを相談できる相手はおらず、孤独感は深まるばかりです。
この精神的な負担は、「気合」や「根性」で乗り越えられるものではありません。
精神的に追い詰められる
起業家がいかに精神的に追い詰められやすいかを示すデータがあります。アメリカのある調査では、起業家はそうでない人と比べて、うつ病になる確率が2倍、ADHDが6倍、そして双極性障害(躁うつ病)に至っては11倍も高いという衝撃的な結果が出ています。これは、起業という行為が、人間の心に異常なほどの負荷をかけることを示しています。
これらの要素は、互いに悪い影響を与え合い、抜け出すのが難しい悪循環を生み出します。事業がうまくいかないストレスで、創業者の心は疲弊します。心が疲弊すると、冷静な判断ができなくなり、事業はさらに悪化します。そして、それがまた新たなストレスを生むのです。
今の仕事のストレスから逃れたいと願って起業を志す「起業したいけどアイデアがない」人にとって、この現実はあまりにも皮肉です。
会社員時代のストレスとは比べ物にならないほど、遥かに深く、複雑なストレスの渦の中に、何の準備もなく飛び込もうとしているのですから。
なぜ「アイデア」が事業の命綱なのか?
なぜ、「アイデアがないままの起業」はこれほどまでに危険なのでしょうか。それは、優れたビジネスアイデアが、単に「何を作るか」という設計図ではなく、荒波を進むための「コンパス」であり、会社の存在理由そのものである「北極星」だからです。
アイデアがないということは、コンパスを持たずに大海原へ漕ぎ出すのと同じことなのです。
製品を作るだけじゃない。アイデアは会社の進むべき道を示す「コンパス」
力強いビジネスアイデアの中心には、いつも「誰の、どんな問題を解決するのか」という明確な答えがあります。この答えこそが、会社の「ビジョン(目指す未来)」や「ミッション(果たすべき使命)」の源泉となります。
ビジョンやミッションは、壁に飾っておくためのかっこいい言葉ではありません。人々の採用、商品の宣伝、新しい機能の開発、資金集めといった、会社が行うすべての判断の基準となる、とても実用的な指針なのです。
例えば、人を採用するとき。明確なミッションがあれば、「なぜうちの会社で働くべきなのか」という問いに力強い答えを出すことができ、同じ価値観を持つ優秀な人を引きつけることができます。
商品を宣伝するときも、解決する問題がはっきりしていればいるほど、ターゲットとなるお客さんの心に響くメッセージは鋭く、具体的になります。
逆に、この「なぜ」が欠けている会社は、コンパスを失った船のように、ただ漂うことになります。市場の流行やライバルの動きに振り回され、その場しのぎで一貫性のない判断を繰り返してしまうでしょう。
そんな事業では、創業者が自分のビジネスに「誇り」を持ち、困難な状況でも粘り強くお客さんに価値を訴え続けるための心の支えを持つことはできません。
アイデアとは、事業に魂を吹き込み、会社全体を一つの方向へと導く、なくてはならない力なのです。
アイデアの真価が問われる究極のテスト:プロダクトマーケットフィット
スタートアップの世界で最も重要で、そして最も誤解されがちな言葉が「プロダクトマーケットフィット(略してPMF)」です。
PMFとは、簡単に言えば「自分たちの作った商品やサービスが、特定の市場のお客さんに熱狂的に受け入れられ、『これじゃなきゃダメなんだ!』と求められ、喜んでお金を払ってくれる状態」を指します。
これは、事業が自力で成長していくための「離陸点」であり、スタートアップが目指すべき、最初にして最大の関門です。
PMFを達成するまでの道のりは、まさに「アイデアを検証し続ける旅」そのものです。創業者が最初に抱いた「この問題は、この方法で解決できるはずだ」という仮説を、市場という名の実験室で何度も試し、お客さんからの声を聞いて商品を改良し続ける、地道なプロセスなのです。
PMFの達成は、創業者のアイデアが単なる思い込みではなく、市場に受け入れられた「事実」であることの証明に他なりません。
ここで、「起業したいけどアイデアがない」人が直面する根本的な問題が明らかになります。このPMF達成への旅を始めることすらできないのです。なぜなら、検証すべき「仮説(=アイデア)」を持っていないからです。
それでも挑戦したいあなたへ。リスクを減らし、成功確率を上げる方法
これまでの話で、軽い気持ちでの起業がいかに危険か、お分かりいただけたかと思います。しかし、「それでも、挑戦したい」という心の炎が消えない人もいるでしょう。
この章では、リスクをできるだけ小さくし、成功の確率を少しでも上げるための、具体的な方法をお伝えします。
4.1 アイデアは「ひらめく」な!「問題」を見つけに行こう
まず、考え方を180度変える必要があります。「何か良いアイデアはないかな?」と頭をひねるのは、もうやめましょう。
あなたがなるべきは、問題発見のプロです。素晴らしいビジネスは、いつも世の中にある「不便だな」「イライラするな」「もっとこうなればいいのに」という現実の悩みから始まっています。以下の方法は、その「問題」を見つけるための具体的なアクションプランです。
- 自分自身を深掘りする
あなたが得意なこと、これまでの仕事で得た経験、夢中になれることは何ですか?今までどんな壁にぶつかり、どう乗り越えてきましたか? あなたの経験の中にこそ、他の誰も気づいていない問題が眠っているかもしれません。 - 身の回りをじっくり観察する
あなた自身や家族、友人が、毎日の中で感じている「ちょっとした不便」を、スマートフォンのメモ帳にでも書き出してみましょう。「こんなのがあったら助かるのに」という小さな不満が、大きなビジネスのタネになることはよくあります。 - 組み合わせたり、応用したりする
すでにある2つのサービスを組み合わせて、新しい価値を生み出せないでしょうか?海外で流行っているビジネスを、日本の市場に合わせて少し変えてみたらどうでしょう? ゼロから全く新しいものを発明する必要はないのです。 - 発想ツールを使ってみる: マンダラートやSCAMPER法といったフレームワーク(思考の枠組み)は、考えを整理し、新しい視点を与えてくれます。アイデアが行き詰まった時に、思考の壁を壊す手助けをしてくれるでしょう。
いきなり会社を辞めるな!賢く始める「お試し起業」
起業の成功物語は「人生を賭けた大勝負」を美しく描きがちですが、賢い起業家はリスクを徹底的に管理します。アイデアが本当にうまくいくかどうかは、会社を辞めて人生を賭ける前に、しっかり試すべきです。
- 「副業」から始めてみる
アイデアを試し、ビジネスを立ち上げる上で、最も安全で効果的な方法が「副業」です。会社員として安定した給料をもらいながら、市場の反応を見たり、最初のお客さんを見つけたり、ビジネス運営の練習をしたりできます。これは、もし失敗しても路頭に迷うことのない、最高のセーフティネットです。 - 自分の「得意分野」で戦う
あなたがすでに詳しい知識を持っている分野で起業することは、リスクを劇的に下げます。全く知らない業界でビジネスを始めると、「業界の勉強」と「経営の勉強」という2つの巨大な課題を同時にこなさなければなりません。これは創業者を簡単に疲れさせ、燃え尽きさせてしまいます。 - MVP(実用最小限の製品)を作ってみる
何ヶ月もかけて完璧な製品を作るのではなく、アイデアの「一番大事な価値」だけを試せる、最低限の機能を持った試作品(MVP)を素早く作り、実際のお客さんに使ってもらうのです。これにより、無駄な開発にお金を使うのを防ぎ、お客さんが本当に求めているものへと製品を育てていくことができます。
「この問題を解決したい!」という情熱の力:2つの成功事例
強い「問題意識」が、いかにビジネスを成功に導くか。2つの素晴らしい会社の物語が、その力を証明しています。
株式会社ユーグレナ
- 出会った問題
創業者の出雲充さんは、大学時代に訪れたバングラデシュで、子どもたちが栄養失調で苦しんでいる現実を見て、大きな衝撃を受けました。この「世界の食料問題を解決したい」という強烈な体験が、彼の揺るがないミッション(使命)になりました。 - 見つけた解決策
彼はその解決策として、驚くほど栄養価の高い小さな藻「ユーグレナ(ミドリムシ)」に可能性を見出しました。 - 驚異的な粘り強さ
「ミドリムシで世界を救う」という大きなビジョンは、彼に超人的な粘り強さを与えました。事業を始めてから、彼は2年間で500社に営業に行き、そのすべてに断られ続けたのです。もし彼のアイデアが、単に「ミドリムシを売るビジネス」だったら、これほどの失敗に耐えられたでしょうか。きっと無理だったでしょう。彼を支えたのは、製品そのものではなく、その先にある「問題を解決する」という大きな目的だったのです。
dely株式会社(クラシル)
- 見つけた問題
創業者の堀江裕介さんは、最初、料理の宅配サービスで失敗を経験しました。しかし彼は諦めず、市場の変化とユーザーが何を求めているかを注意深く観察し続けました。そして、動画コンテンツが流行り始め、人々が料理のレシピをもっと簡単で分かりやすく知りたいと願っていることに気づき、そこに「絶好のチャンス(好球)」を見出したのです。 - 進化する力
彼は失敗から学び、市場の声に耳を傾け、事業を料理動画サービス「クラシル」へと大胆に方向転換させました。 - ここから学べること
クラシルの物語は、アイデアが一度きりの「ひらめき」ではないことを教えてくれます。それは、市場との対話を通じて常に試し、進化させていくべき「仮説」なのです。最初に考えた問題が間違っていることもあります。しかし、本当に大切なのは、その失敗から学び、お客さんが本当に困っていることを見つけるまで、粘り強く「問題を探し続けるプロセス」そのものなのです。
起業家が直面するストレスは、一つではありません。以下の表は、その代表的なものをまとめたものです。これこそが、覚悟を決めたあなたが乗り越えなければならない、リアルな壁なのです。
| ストレス要因 | 具体的にはどんなこと? | 判断への影響 | 心と体への影響 |
|---|---|---|---|
| お金の不安 | 収入が不安定、資金が尽きるかも、自分のお金も減っていく。 | 目先の利益ばかり考え、長期的な視点を失う。 | 常に不安、よく眠れない、「金銭的な不安」が頭から離れない。 |
| 責任とプレッシャー | 従業員の給料、投資家の期待、お客さんをがっかりさせられない。 | 失敗を恐れすぎる、仕事を任せられない、細かく口出ししてしまう。 | 燃え尽き症候群、極度のプレッシャー、逃げ場がないと感じる。 |
| 孤独感 | 社内に本音で話せる相手がいない、悩みを共有できない。 | 自分の考えが正しいと思い込む、多様な意見が聞けない。 | 「孤独」を感じる、うつ状態になる、誰にも理解されないと感じる。 |
| 仕事の多さ | 少ない人数で営業、宣伝、経理、事務など全部やる。「バックオフィス地獄」。 | 戦略を考える余裕がなくなり、その場しのぎの対応に追われる。 | 慢性的な疲れ、仕事から離れられない、体の不調。 |
| 市場からの圧力 | 常に新しいものを求められる、ライバルへの恐怖、批判的な意見への対応。 | 焦って方向転換する、考えすぎて動けなくなる。 | 自分は偽物だと感じる(インポスター症候群)、批判に過敏になる。 |
結論:あなたが解決したい「問題」はありますか?
起業を夢見る多くの人は、スタートの順番を間違えています。「起業家になる」という状態や肩書きをゴールに設定し、そのための手段として、後からアイデアを探し始めます。
ただ「起業家になりたい」と願うのをやめてみませんか。そして、好奇心を持って世界を観察する「問題発見のプロ」になってみませんか。
「この世界で、何が壊れているだろう? 何が不便で、誰が困っているだろう? そして、他の誰でもなく、なぜ自分だけが、それを解決せずにはいられないほど、その問題に心を奪われているのだろう?」
この問いに対する、あなただけの、魂のこもった答えを見つけ出すこと。それこそが、起業家になるための、唯一の、そして本当のスタートラインなのです。